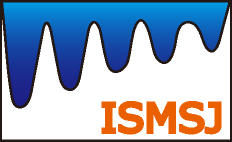第13回 常識の揺らぎから考える「常識を疑う」ということ
2020 年 6 月 19 日
スタンフォード大学 睡眠医学センター
河合 真
前回の記事からまたもや随分と時間が経ってしまった。その間にCOVID−19のパンデミックという大事件が起きて、多くの死者が出ている。このパンデミックにより人々の仕事、生活は大きな変化を余儀なくされてしまった。当たり前だが、国際学会は軒並みキャンセル、日本への出張も全て取りやめになった。今現在も国によって感染対策は色々なフェーズにあり、私がいるカリフォルニア州でも外出禁止令が段階的に解除されていく状況でこの先どのような変化が起きるのか戦々恐々として見守っている。そして皆さんと同様に私の生活も変化を余儀なくされた。
多くの死者が出て、失職する人がいる中で、仕事があり、感染もしていない状況をまずは感謝したいし、まず生き延びることが何よりも優先されるべきだ。だからこそ変化に順応したいと思っている。皆さんの周りでも順応しなければならない状況があるだろう。私が勤務するスタンフォード大学睡眠医学部門も例外ではない。小さなことから大きなことまで様々な変化が起きた。まず、握手がなくなった。米国のベッドサイドマナーのビデオでも必ず出てくる最初の自己紹介と同時にする握手の習慣が綺麗さっぱりなくなった。ハグなんぞはもってのほかである。さらに米国ではあれほど普及しなかったマスクを患者も医療従事者も一般の人たちもするようになった。効果に関しては諸説あるようだが、驚きの変化だ。手洗いに関しては普段から徹底していたので仕事場では変わった印象はなかったが、プライベートでもせっせと手を洗うようになった。
そして、外来だが、3月くらいまではいつものインフルエンザ程度の対応で何とか外来を続けていくのだろうと思っていたら、「質問票を記入するペンが共有されていて不潔だ」と言う声が患者の側から出始めたり、「患者の中に咳の症状があるのに申告せずにそのまま受診した」などの問題が出始めた。患者も医療従事者の側もいつもとクレームの種類が違うのでおかしいなと思っていたら、あれよあれよと言う間にビデオ診療に移行することになった。ビデオ診療とは、患者は自宅にいて病院ウェブサイトにアクセスする。そして、医療従事者とビデオ通話で外来診療をするのである。最初私は外来に通勤して、病院からビデオ診療をおこなっていた。しかし、「睡眠医学科の医師は病院に来るリスクを負わず自宅から診療しろ!」と病院からお達しが出て4月からは全面的に患者、医師共に在宅のビデオ診療が始まった。「自分のパソコンだとうまくソフトが動作しなかったらいやだなあ」と思っていたら病院からメールがきて、ビデオ診療が確実にできるように予め全ての必要なソフトをインストールした新品のラップトップPCがあっと言う間に準備されて医師に配布された。さらに、鈍い私が「えー、ビデオ診療で保険請求いつもどおりできるのかいな?」と思っていたらあっという間に保険請求の基準が改正されて、ビデオ診療でも対面診療と同じように保険請求ができるようになってしまった。
この間2−3週間しかかかっていない。診療継続することが組織の存続に関わることは明らかだったので私も「ビデオ診療でも診療を続けないとまずいだろうな。病院が財政難になって給料とかに響くと嫌だなあ」なんてことを漠然と考えているうちに、病院の執行部は本当にあっという間に診療体制を変更してしまった。この「速さ」は日本人の私からすると「まあ、きっと2―3ヶ月喧々諤々やってようやく移行するのかもなあ」と思っていたので単位が違う驚きの速さだった。アメリカの有事への対応の速さは今まで体験したことがなかったので、まさに「すごい」の一言だった。日本だと、変更する前に会議で何回もコンセンサスを得るプロセスを経てようやく変更することが多い。今回は「変更します。不具合にはできる限り対応しますから言ってください。」だった。「有事の際のスピード」は日本の組織の意思決定に絶対的に足りていないものだと感じた。
そして4月から在宅ビデオ診療が始まったのだが、もちろん最初は患者も医師も慣れていないこともあり、どうしてもビデオにアクセスできなかったり、音声が途切れたり、かなりトラブルが相次いだ。
そんなことがあったので「対応が冷たい」だの「ビデオだけではコミュニケーションが難しい」というクレームが患者からバンバン来るかと待ち構えていた。しかし、この状況では患者の側も外出して、わざわざ本当にリスクの高い病院に行きたくないこともありクレームはほとんどなく、あっさりと移行を受け入れてくれた。
「ドクター河合に直接会いたい」などという患者は全くおらず、ビデオ診療は好評だった。患者数も慣れてくるとある程度こなせるようになってきた。もちろん診察ができないどうにもならない短所はあるのだが、睡眠医学は「患者から話を聞く」ことができればある程度なんとかなってしまうものだということも実感した。もちろん診療科によっては無理なこともあるだろうが、このビデオ診療のオプションができたことは今後感染症が流行したり、私が昨秋のように日本に台風で足止めをくらったりしても外来ができることを意味するので「災害に強い」医療体制ができつつあるとも言えるだろう。
さらに、ビデオ診療には睡眠医学上思わぬ利点があった。実はこのことを共有したかった。睡眠医学でよく強調されることが「患者の生活の中で治療せねばならない」ということがある。睡眠医学で患者の指導をすることが多いのだが、人それぞれいろいろな生活様式を営んでいるし、住んでいる家の構造も違う。一般的に勧められている方法が通用しないことがあるのだ。
ある40代の女性の患者が、「CPAPをしていて効果があるのだけど物音で中途覚醒してしまう。」と常々言っていた。そして、その夫も私の患者なのだったのだが、今までは別々に予約をとって来院してきていた。ビデオ診療になってまとめて二人で予約を取ってくれて夫婦二人を同時に診察することになった。夫婦とはいえプライバシーの問題もあるが、この夫婦は気にする様子もなく二人同時のビデオ診療をした。そして、二人のCPAPの設定を確認することになり、スマホを片手に二人の寝室を見せてくれることになった。でかいベッドの両脇に各々のCPAPが置いてある。妻の方のCPAPは問題なさそうだった。夫の方のCPAPからはマスクから盛大にエアが漏れていることがわかり、妻の中途覚醒の原因が夫のCPAPのエア漏れの音であると思われたために夫のCPAPのマスクのフィッティングを調整することと圧の調整をしたところ、この夫婦の睡眠は今までになく良くなった。これは別々に外来で診療しているうちには気づかなかったことだ。さらに、「なぜかCPAPがすごく汚れて、出てくる空気が埃っぽい」という訴えをする人がいたが、ペットの犬が寝室で寝ていてそのすぐそばの床にCPAPが置かれているのを発見したので、ナイトスタンドを買ってその上に置くように指導した。また、早朝覚醒するという人の寝室の窓にカーテンがないばかりか、異常に広くて朝日がガンガンに差し込むので日の出と同時に起床してしまうことがわかった。
このように睡眠医学が「患者の寝室をみる」ことの重要性を今まで強調してこなかったことを不思議に思うほど新たな発見があった。
さらに、睡眠医学では睡眠時間の延長をよく勧めるのだが、この状況になってテレワークが進み容易に睡眠時間が延長することができるようになった。ここぞとばかりに指導をしている。何しろ「睡眠不足を訴えているのに、睡眠時間を延ばすことをやってみる」ことさえできない人が多かったのだが、それはほとんどの場合通勤時間が長いことが一因である。そしてやってみると何らかの利益を感じることが多くそのまま行動変容に繋がっていく。ある中年男性でOSASがあり、長年CPAPを使用していたが、日中の眠気が残る患者がいた。睡眠時間が4−5時間なので、睡眠時間を延長するように外来のたびに指導しても延長できなかった。しかし、ここ数ヶ月テレワークに移行したことに伴い初めて睡眠時間を延長することが可能になると、眠気がなくなり、本人も驚いている。このような以前の常識ではあり得ない変化が起きている。
COVID−19の流行により常識が崩される状況だが、悪い常識や習慣が崩されることで睡眠医学としては解決につながることも経験した。もちろんいろんな不平不満はあるし、普通に診察がしたいのは山々だ。しかし、そんな状況の中でどうにも動かなかった患者の睡眠の悪い習慣や常識が変化している。今こそ、よき方向へ導くチャンスと考えられないだろうか?
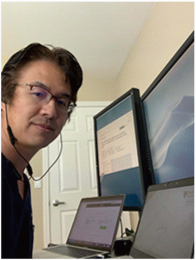
最近の自宅での外来風景。ラップトップコンピューター数台とモニターとヘッドフォンで外来をやっている。そして床屋が禁止になったので髪がかつてないほどのびた。後世のCOVID−19流行時の外来風景として記録用に撮影。
追記:REM睡眠行動異常症(REM Sleep Behavior Disorder)の報告者であるDr. Mark Mahowaldが亡くなった。また一人睡眠医学のレジェンドを失うことになった。心よりご冥福を祈りたい。
https://worldsleepsociety.org/in-memoriam-mark-mahowald/
幸運にも私は睡眠医学フェローの時に月一回ミネソタからスタンフォードに教えに来てくれる彼の外来で直接指導を受けることができた。
卒業後も私の外来日と彼の指導の日が重なっていたこともあり、よく指導医詰所でいろんな話をしたことを思い出す。
「若年者のRBDはとりあえずナルコレプシーを考えろ」「overlearned activity(日常生活においてあまり皮質で考えなくてもできるような行動のこと。例としては自宅内の部屋から部屋への移動、階段の昇降、冷蔵庫を漁るようなこと)ならパラソムニアで生じうる」
「高齢者のOSASを治療するかどうかは利益が何かをよく考えろ」などという敢えて簡潔に言い切る教育スタイルはフェロー達に非常に好評で彼の外来は見学のフェローや訪問者で賑やかだった。
フェローによるプレゼン→ディスカッション→実際に患者をみる→さらにディスカッションというアメリカでも近年はほとんど許されない古典的医学教育スタイルだった。
その結果彼の言葉は私を始め多くの医師の中に今も生きている。そして、私もそれを後進に伝える義務があると思っている。教育とは誰かの中で生き続けることだ。だからこそ尊い。
あのスタイルは彼自身も一線から退いていたからこそできたのだと思うが、私も体力的に厳しくなったらああいう教育中心の外来をやってキャリアの最終章にしたいと思っている。
Mahowald先生、あなたの教えはちゃんと次世代に伝えます。どうぞ安心してお休みください。